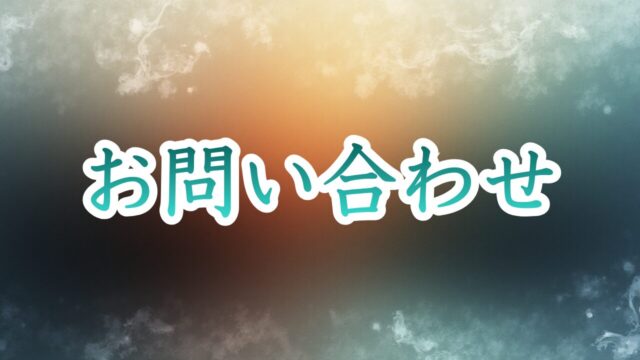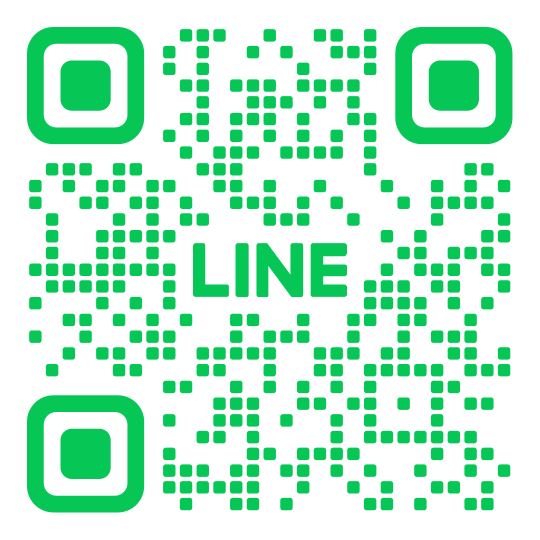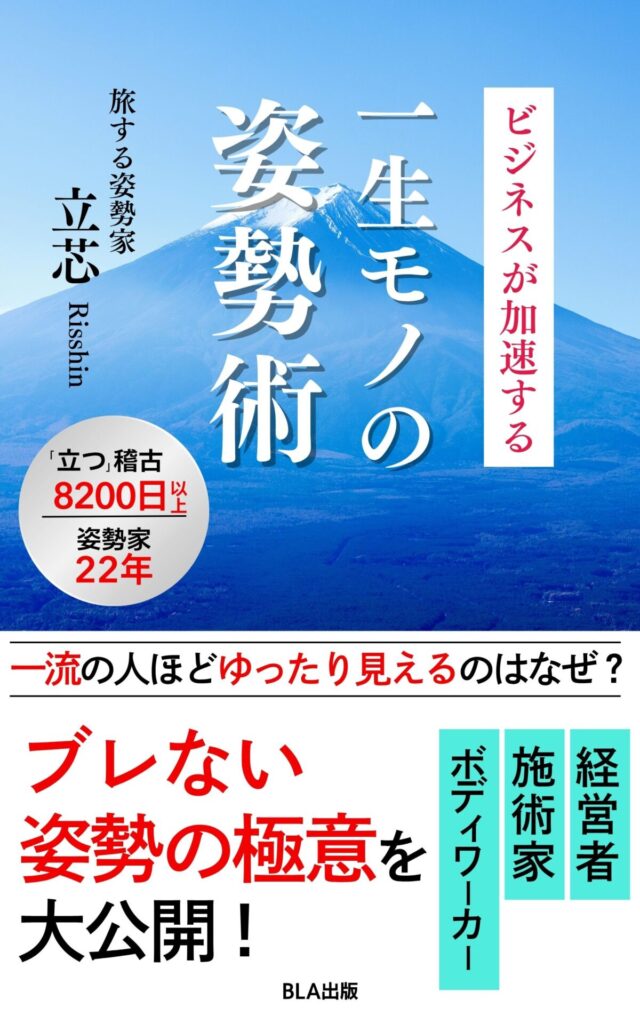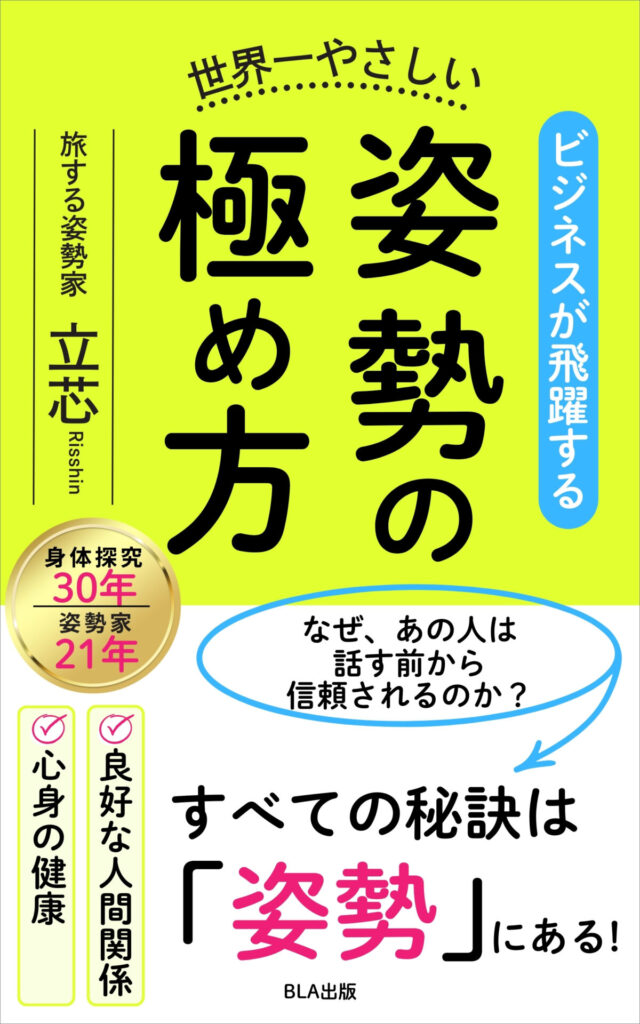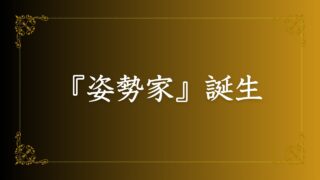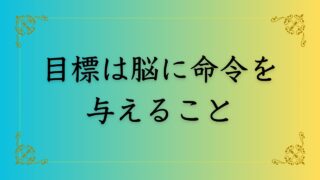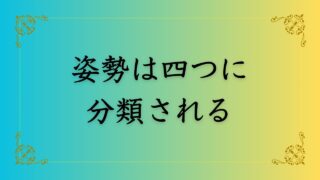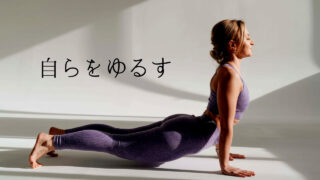著書「目の見えない人は世界をどう見ているのか」を読んで鳥肌が立った部分がありました。それは僕自身の身体との会話する感覚にあまりにも似ていたので紹介したいと思います。
本の中で、ある盲目の子どもが美術の授業で粘土で立体物を作るという課題に取り組んでいたそうです。その子どもは壺を作りはじめたのですが、その過程の中で目の見える人とは違うことが起きたことが書かれていました。
違うこととは、
その子どもは壺の内側に細かい細工を施し始めたとありました。
これがどういう意味か分かるでしょうか?
目の見える人にとっては壺というものがある場合、眼で見える表側に色を塗ったり模様を作ったりすることが普通ではないでしょうか。
間違っても壺の中、内側に色々と細工を施すことは通常発想に出てこないのではと考えます。
なぜなら、壺の内側は「見えない」からです。
ですが盲目の子どもは、眼では見えないが故に壺に内側、外側という概念がなく、全てを観ているのだということでした。
これには正直鳥肌が立ちました。
モノの見方がまるで違う。
見えているのに見えていない。
見えないのに見えている。
どちらが良い悪いといったことなどではなく、まさしく観ている次元が違う。
そう感じました。
そしてこの感覚は身体の「内観」という話をした時に、自分の言う内観と相手の思う内観の感覚の違いもここにあったのかと感嘆しました。
ここで言う内観とは、
自身の身体の中から湧き出る力の出所などを探る時に使用したりする言葉です。
今思えばですが、
内観という会話をしたときに
通常感じるのは外側から観た身体の中というイメージが大多数なのではないでしょうか。
本当の意味で身体の中から身体の中を見つめる目線。
その感覚が僕のいう内観の意味です。
この本のおかげでようやく身体の「内観」について言語化が出来た気がします。
感覚を研ぎ澄ます。
その為にはその感覚がそもそも無い前提で考えることが良いということが判明し、とても勉強になりました。