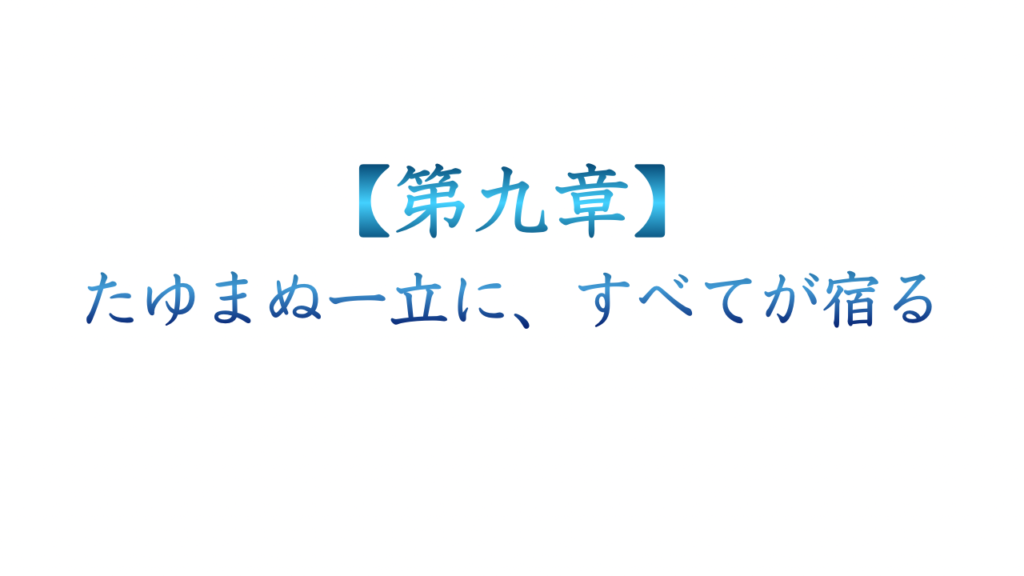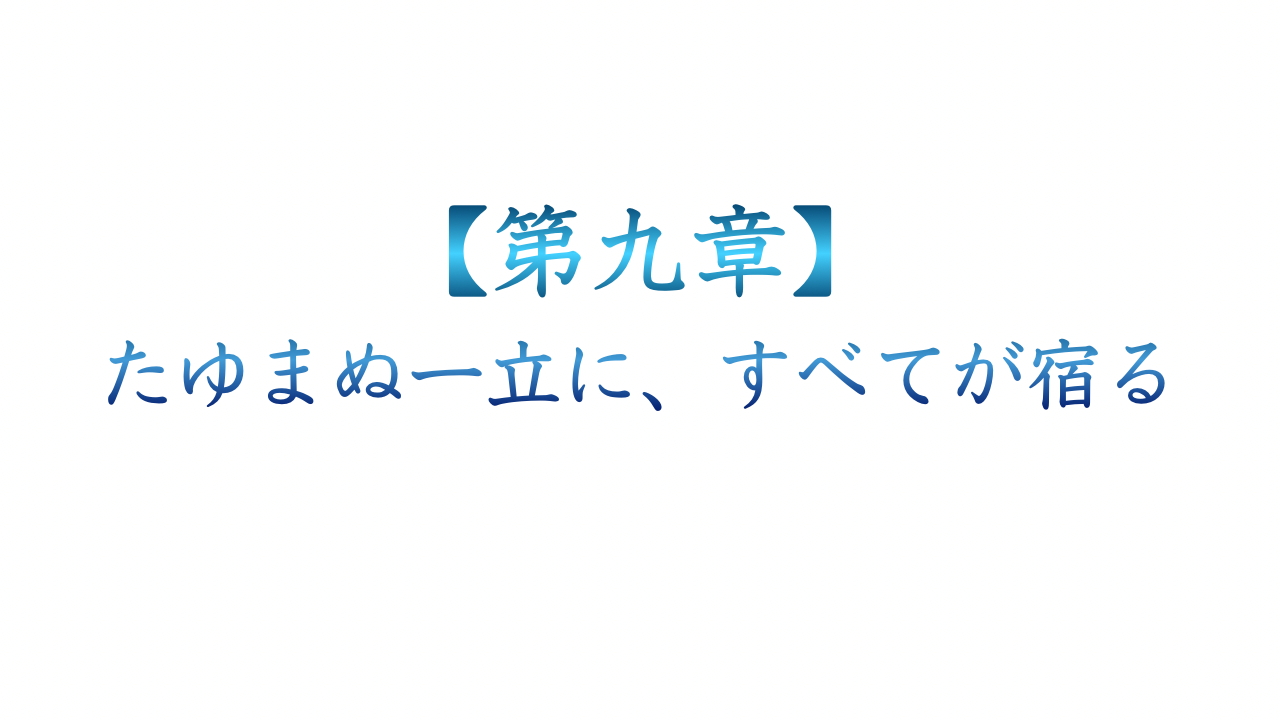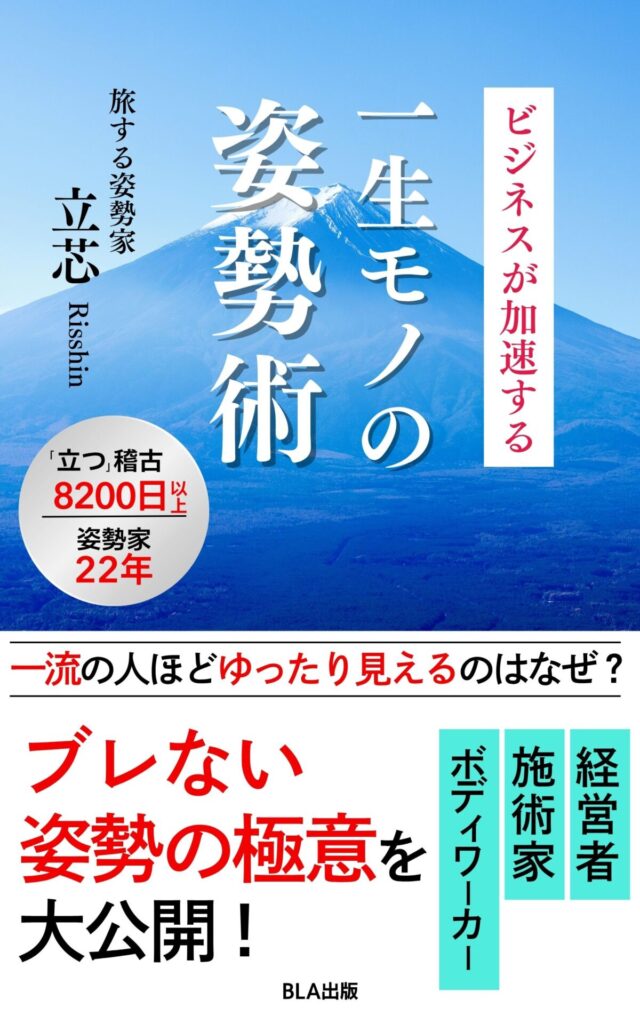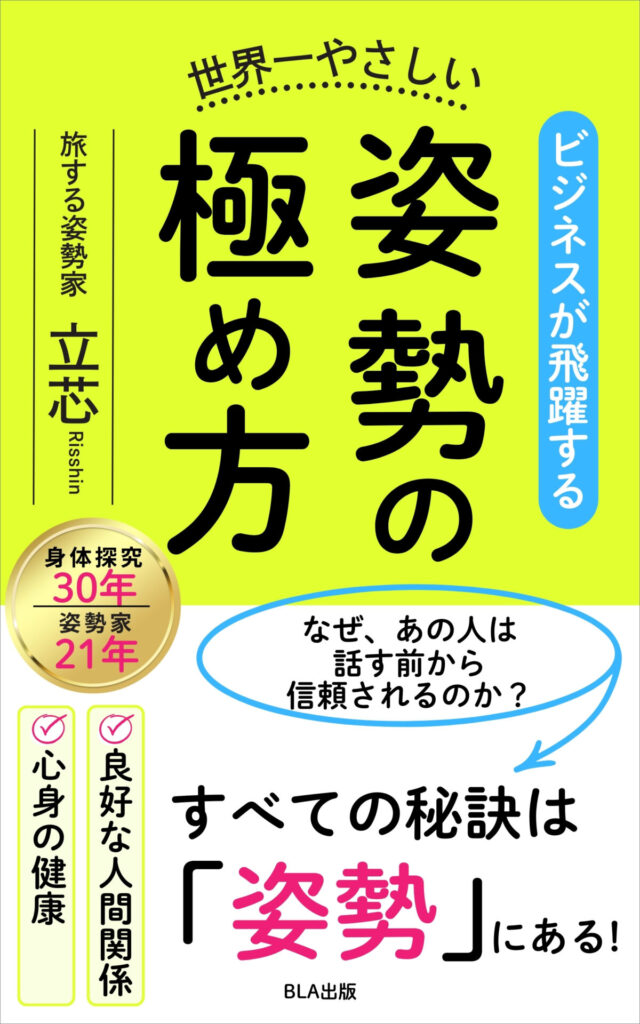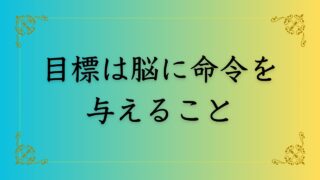夏の風が、川の水面をきらきらと揺らしていた。
太郎はいつもの河川敷に立っていた。
だが、今日の彼はもう「弟子」ではない。
立芯が去ってから三ヶ月。
ひとりで立つ時間が、今では日々の儀式になっていた。
(立つことで、こんなにも世界が優しく見えるなんてな……)
最初は意味が分からず、反発ばかりだった。
けれど今は、あの静けさが恋しい。
立つたびに、心の奥に師匠の声が響く。
「立ちなさい。迷ったら、立てばいい。」
太郎は笑った。
この言葉、何度助けられたことか。
その時だった。
少し離れたところで、一人の女性がふらつきながら立っていた。
五十代くらいだろうか。
買い物袋を片手に、足元を気にしながら小さく息をついている。
太郎は思わず声をかけた。
「大丈夫ですか?」
女性は驚いたように顔を上げた。
「ええ、ありがとう。でも最近ね、膝が痛くて……
歩くのが、ちょっと怖いの。」
太郎は、少しだけ微笑んだ。
「もしよかったら、立つだけの方法、試してみませんか?」
「立つだけ?」
「はい。運動でも治療でもなくて、立つことから始めるんです。
僕も、最初はそれしかできませんでした。」
女性は半信半疑の表情で立ち上がった。
太郎は優しく言葉を添える。
「足の裏で地面を感じて、
肩の力を抜いて、
息を、少し長めに吐いてみてください。」
風が二人の間を通り抜けた。
ほんの数十秒。
女性の顔に、少しだけ柔らかな表情が浮かんだ。
「……あら、不思議ね。
なんだか、身体の中が静かになった気がする。」
太郎は笑った。
「それが“立つ”なんです。師匠に教わりました。」
女性は目を細めた。
「あなた、いい顔してるわね。
なんていう方?」
「太郎です。」
「太郎さん、ありがとう。
こんな立ち方、教わったの初めて。」
そう言って去っていく彼女の背中は、
ほんの少しだけ、凛として見えた。
太郎は空を見上げた。
夕焼けの空に、立芯の笑顔が浮かぶ気がした。
(師匠……。
僕、やっと分かりました。
“立つこと”って、もらうことじゃなくて、渡すことなんですね。)
風が吹いた。
その風の向こうに、また新しい出会いの予感があった。
太郎の“自作の道”――それは、
次の誰かに“立つ”を伝える旅の始まりだった。
《終章の気づき》
立つとは、誰かの痛みに気づく姿勢。
立ち続けるとは、その痛みを優しさに変える生き方。
そして、“たゆまぬ一立”とは――
生命が生命を支え合う、最も静かな奇跡である。
(完)
次回【エピローグ】立芯、笑いながら立ち返る