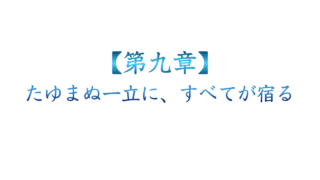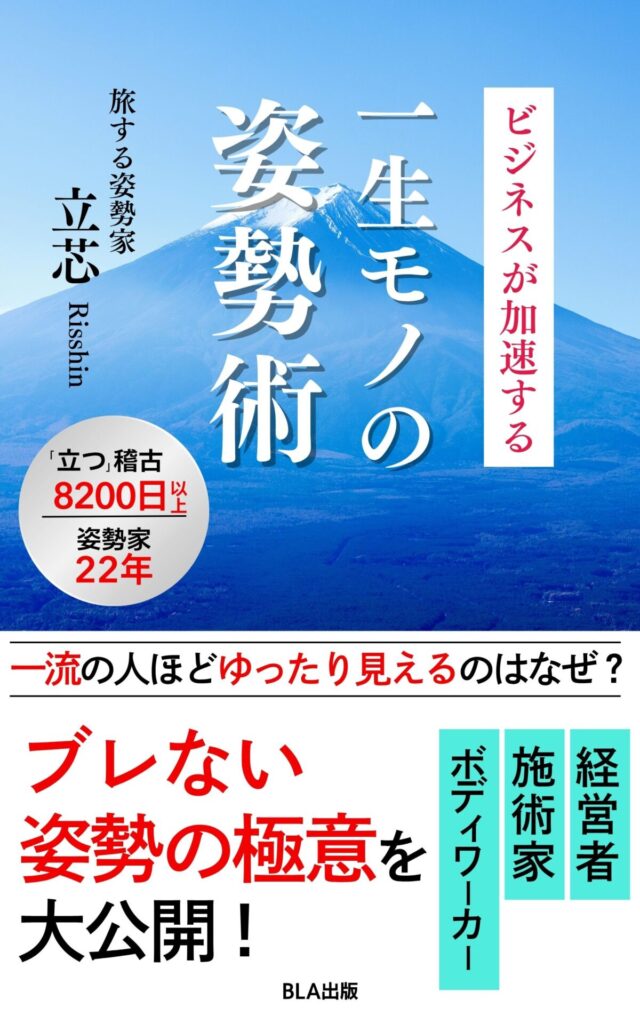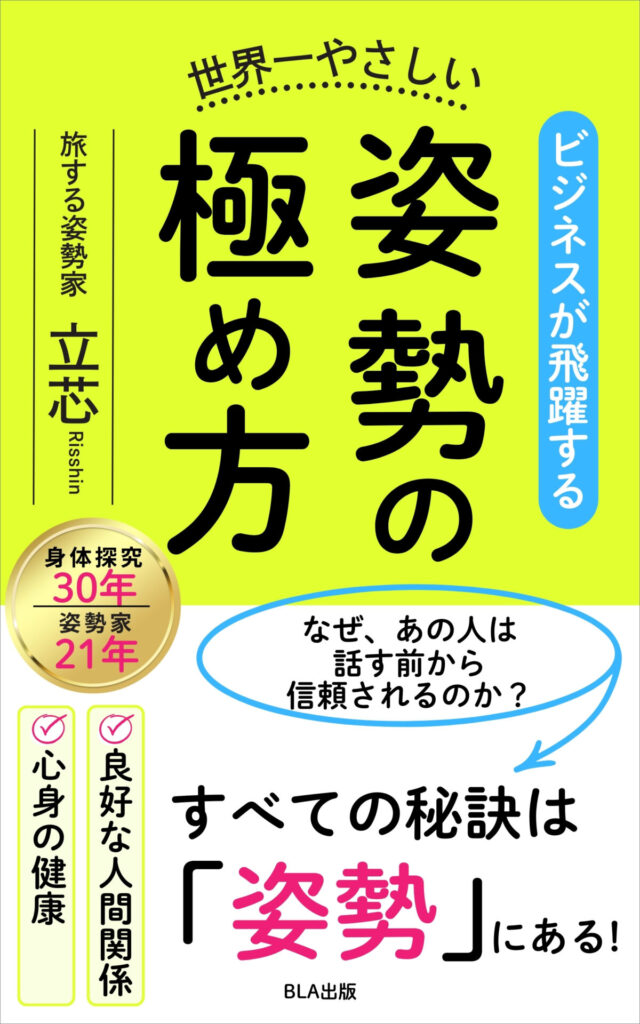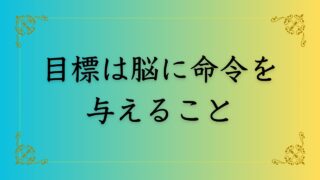春の終わり。
河川敷の草が、また少しだけ伸びていた。
風はあたたかく、夕日が川面を金色に染めている。
太郎は、いつもの場所で立っていた。
だが、今日だけは少しだけ胸がざわついている。
(師匠、今日も来るかな……。)
そこへ、背後から静かな声が届いた。
「もう、立ててるね。」
「師匠!」
振り返ると、立芯がいつものように立っていた。
何も変わらない――けれど、なぜか今日はその姿が少し遠く感じた。
「太郎くん、今日は最後の課題を出そう。」
「え、最後!? もう卒業ですか!?」
「うん。今日で“立つ稽古”はいったん終わりだ。」
「……なんか寂しいなぁ。」
「はは。立てるようになった人間に、僕ができることはもうないよ。」
立芯は空を見上げながら、
ゆっくりと話し始めた。
「太郎くん。
“立つ”ってね、自分のためにやるうちは、まだ“修行”。
でも、“誰かのために立つ”ようになった時、初めて“道”になる。」
「……誰かのために、立つ……。」
「うん。
自分が整うと、人は自然と他人を整えたくなる。
それは押しつけでも教育でもなく、“響き”なんだよ。」
太郎は静かに頷いた。
「師匠、それって、姿勢で人を救うってことですか?」
「姿勢で“救う”んじゃない。
姿勢で“寄り添う”んだ。」
太郎の目が少し潤んだ。
風が止まったように感じる。
立芯はふと笑って言った。
「僕が教えてきたのは、“立つこと”じゃない。
“生き方の芯”を思い出すことなんだ。」
「……師匠、最初に言ってましたね。
“たゆまぬ一立に、すべてが宿る”って。」
「そう。
立つって、生きることそのものなんだよ。」
「……でも、師匠。
僕がまた迷った時は、どうすればいいですか?」
立芯は少し間を置いて、穏やかに笑った。
「その時は――立ちなさい。」
「……やっぱり、それか。」
「“立つ”って、迷いの中心に戻るスイッチなんだ。
動けない時こそ、立てばいい。」
太郎は深く息を吸い込み、まっすぐ立った。
川の風が、静かに身体を包む。
「師匠、これからどうするんですか?」
「僕? また、次の誰かに会いに行くよ。
立てなくなった人は、どこにでもいるから。」
「……そうですか。」
「でも、太郎くん。
君がこれから立ち続ければ、もう僕はいらない。」
立芯は、そう言って帽子を軽く押さえ、
ゆっくりと夕日の中へ歩いていった。
その背中は、風と一つになって消えていった。
太郎は、しばらくその場に立ち尽くしていた。
胸の奥が、じんわりと温かい。
そして、ぽつりと呟いた。
「……俺も、誰かのために立てる人になろう。」
その瞬間、川面に映る夕日が、まるで頷くようにきらめいた。
《第八章の気づき》
人は誰かに支えられて立ち、
いつか誰かを支えるために立つ。
“立つ”とは、命のバトンを受け渡す行為である。
次回【第九章】たゆまぬ一立に、すべてが宿る